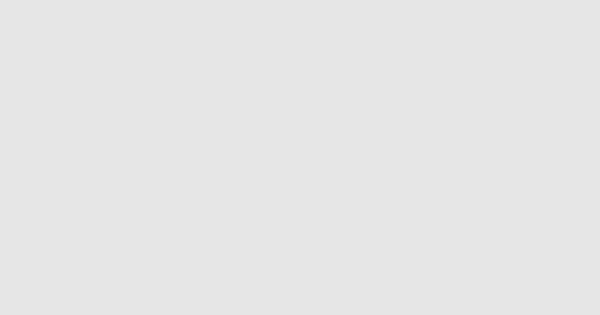お気軽にご相談ください
著作権や商標、IT・知財法務にお困りなら
お気軽にご相談ください
ソフトウェアの著作権とは?企業が知っておくべき契約とトラブル対策
「ソフトウェアの著作権は、どこまでがベンダ側に帰属するのだろうか」
「ソフトウェアの費用を払ったのに著作権を持っていないと言われた」
そんなトラブルに巻き込まれていませんか?
ソフトウェアは一見“モノ”のように思えますが、実際は「著作物」として扱われ、知的財産権のルールが適用されます。
契約時にその認識があいまいなままだと、納品後に深刻なトラブルに発展する可能性もあります。
この記事では、ソフトウェアにおける著作権の基本から、契約で起きやすいトラブル事例、発注企業側のリスク対策までをわかりやすく解説します。
なぜソフトウェアにも著作権があるのか

弁護士
野俣 智裕
ソフトウェアは「著作物」に分類される
著作権法では、言語・音楽・絵画などと同様に、「プログラム(ソフトウェア)」も著作物として扱われます(著作権法第2条1項10号の2参照)。
著作権は創作と同じタイミングで作り手に発生する
著作権は、特許や商標と違って「出願」や「登録」をしなくても自動的に発生します。ソフトウェアを創作した瞬間から、開発者(通常はベンダ)が著作権を保有することになります。
そのため、発注企業が「費用を払ったのだから自動的に著作権も自分のものになる」と考えるのは誤りです。契約で明示的に定めない限り、著作権は原則として開発側に留まります。
ソフトウェア契約で起きやすい著作権トラブル

弁護士
野俣 智裕
別会社に類似ソフトが流用されたケース
システム開発を依頼した会社が、納品後にベンダの別クライアントでもほぼ同じソフトを提供していたという事例は少なくありません。
著作権がベンダ側にある場合、再利用は違法ではないこともありますが、発注側からすれば「独自性を確保したかったのに」と納得できないケースもあります。
契約時に著作権の帰属や利用範囲を明確にしておく必要があります。
納品物を修正したら権利侵害と指摘されたケース
軽微な修正やカスタマイズを社内で行った際に、ベンダ側から「著作権侵害に当たる」と警告を受けるケースもあります。
契約で改変権(翻案権)の扱いが不明確なままだと、発注企業側は自由に修正できません。
費用を支払えば著作権も手に入ると思っていた
「開発費を支払えば、成果物は自社のものになるはず」と考えていたが、実際にはベンダに著作権があるため、思うように使えなかった──という誤解は非常に多いです。
納品された成果物の使用と著作権の取得は別物であり、契約で明確に区別して記載する必要があります。
ソースコードをもらえると思っていたが、渡されなかった
運用段階でシステム改修をしたくなったが、ベンダがソースコードを渡してくれなかった、あるいは別料金を請求された、こうしたケースも頻繁に発生します。
契約時に「納品物にソースコードを含めるか」「第三者への改修委託は可能か」といった条件を明確にしておくべきです。
著作権の帰属には複数のパターンがある

弁護士
野俣 智裕
①ベンダが保有し、使用許諾を発注側に与える形
契約形態として、著作権はベンダに残したまま、発注企業に対して「利用許諾」を与える方式です。
この場合、利用範囲(社内利用のみに限定など)や複製・改変の可否などを個別に契約書で定めます。
②既存コードはベンダ、新規開発部分は発注企業に帰属
既存のテンプレートやモジュールはベンダに残し、カスタマイズ部分のみ発注企業に著作権を移転する方式です。
技術資産をベンダが守りつつ、発注企業も独自開発部分に自由度を持てる契約形態です。
③共通部分はベンダ、企業独自部分のみ企業に帰属
ベンダ側の共通ライブラリ・共通仕様と、企業特有の処理やデザインを明確に区分し、それぞれの著作権帰属先を分ける形式です。
「どこからどこまでが共通か」の切り分けが曖昧だと、後々のトラブルの火種になります。
④共同著作とする契約(管理が複雑になる)
両者で共同開発したことを前提に、著作権も共有する形態です。ただし、著作権を共有すると片方だけでは勝手に改変や複製等ができないため、契約上の調整が非常に重要です。
管理が複雑になるため、明確な取り決めができる場合に限って採用すべき形です。
契約書で必ず確認しておくべきポイント

弁護士
野俣 智裕
著作権の帰属を明記する条項があるか
著作権の帰属が不明確なまま契約すると、後に「誰にどの権利があるのか」を巡って争いになることがあります。たとえば、企業が自社システムをリニューアルする際、既存コードを再利用しようとしたら、元のベンダから「著作権は当社にある」と差止請求を受けるという事態もあり得るのです。
そのような事態を防ぐためには、契約書に「本件ソフトウェアに関する著作権は、発注者に帰属する」「本契約に基づく成果物に関する一切の知的財産権を発注者に譲渡する」などの明確な条文を盛り込んでおく必要があります。
ソースコードを受け取るか否かが明示されているか
ソースコードの納品が契約に含まれていない場合、後から追加料金が必要になることもあり得ます。
改修・再委託の自由を確保するためにも、「納品時にソースコードを受け取る」旨を明示しておくことが重要です。
著作者人格権を行使しない旨が記載されているか
著作権には「財産権」だけでなく、「人格権」があります。たとえば開発者が、「名前を消された」「自分の意図しない修正をされた」などを理由に、著作者人格権の行使(氏名表示権、同一性保持権など)を主張する可能性があります。
実務では、こうした主張が発注側の業務を阻害するリスクがあるため、「著作者人格権を行使しない」旨を契約書で明記しておくのが一般的です。具体的には、「開発者は、本契約に基づき納品されるソフトウェアに関して、著作者人格権を行使しないものとする」といった条項です。
この条項がないと、改変や移植のたびにベンダの承諾が必要となるなど、運用上の支障が出るおそれがあります。
発注企業が取るべきリスク対策

弁護士
野俣 智裕
エスクローでソースコードを保管する方法
ベンダが倒産・契約終了した場合でも、業務を継続できるように、第三者機関にソースコードを預けておく「エスクロー契約」を結ぶのも一つの方法です。
特に基幹業務に関わるシステムでは、将来の保守性・修正の自由度を確保する手段として有効です。
ベンダとの関係悪化を想定した契約上の備え
契約終了時に何を返還し、どの範囲まで利用可能とするかなど、フェーズアウト時の取り決めをあらかじめ明記しておくことで、関係悪化時にも冷静に対処できます。
IT契約や知財法に詳しい弁護士への相談
ソフトウェアの契約は専門性が高く、一般的な契約書テンプレートでは不十分なこともあります。
ベンダの契約書をそのまま受け入れるのではなく、IT法務や知財に強い弁護士に一度チェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ
ソフトウェアの著作権は、発注側とベンダ側の間で誤解が生じやすく、契約書のわずかな記載漏れが大きなトラブルにつながることも少なくありません。特に「著作権の帰属」「ソースコードの取扱い」「著作者人格権の扱い」などは、実務に大きな影響を与える重要な論点です。
発注企業としては、「費用を払ったから著作権も自分のものになる」と安易に考えるのではなく、契約段階でリスクを見越した条文を盛り込むことが必要です。さらに、エスクロー契約や関係終了時の取り決めなど、将来的な保守やトラブル時の対応まで視野に入れておくことが、事業継続の観点からも極めて重要です。
ソフトウェアの契約は、高度な専門知識が求められる分野です。自社にとって不利な条件で契約を結ばないためにも、IT契約や知財法に精通した弁護士に早めに相談しておくことを強くおすすめします。
ソフトウェアの著作権契約に不安を感じたら、当事務所までお気軽にご相談ください。